言問小歴史絵巻
更新日:2011年4月1日
言問小学校のあゆみ
1 言問小学校ができたころ
言問小学校ができる前、この地域の子供たちは小梅小か、現在の本所高校の辺りにあった牛島小学校に通っていました。しかし、子供の数が増え続けたため二校とも教室の数が足りなくなってしまいました。
そこで本所区(当時の墨田区は東京市の本所区と、向島区に分かれていました)は新しい小学校を建てることにしました。こうしてできたのが言問小学校です。
言問小は、カネボウの重役だった和田豊治さんの屋敷跡に建てられました。当時はクレーンなどの機械はないので、ほとんどの作業を人力で行いました。
新しい真っ白な鉄筋コンクリートの校舎は、当時としてはとても豪華なものでした。関東大震災(1923年)から、まだ10年ほどしか経ってないときだったので、火にも、地震の揺れにも強い丈夫な校舎は、地域の人から「白亜の殿堂」と呼ばれたそうです。
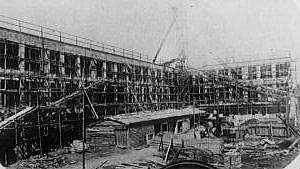
言問小ができたとき、6年生は卒業が近いので、元の学校に残りました。当時は各学年とも4クラスぐらいあり、全校では1041人の子供がいました。
新しい校舎には電動のこぎりやミシン、グランドピアノなど最新の道具・用具がそろえられていました。暖房も、熱い蒸気を教室へ送るスチーム暖房がありました。
校庭も当時の東京市の小学校としてはとても広いものでした。運動会が自分の学校でできると話題になり、見学者が東京じゅうから来たそうです。
しかし、言問小が開校した年に起こった戦争はずっと続いていました。お米なども自由に買えなくなり、ぜいたくなことはできなくなってきました。戦争に備えるため、言問小にも防火用水をためる池が作られました。(この池は戦後プールとして使われています)

2 はげしくなる戦争の中で
太平洋戦争が始まって、人々の生活はますます苦しくなりました。敵の飛行機が爆弾を落としに来る(空襲と言います)ので、安全のため、朝は集団登校になりました。敵の飛行機が来たことを知らせるサイレンが鳴ると、授業中でもすぐ家に帰ることになりました。子供たちの命が危ないということで、田舎の親戚に子供を預けたり、町から引っ越す人も多くなりました。昭和19年(1944)、言問小の3年生以上の子は、集団で千葉県の君津郡に疎開し、そこで暮らすことになりました。
言問小の階段の手すりにあったかざりや、スチーム暖房機は、戦争に使うための金属として取られてしまいました。校舎が白くて大きな目立つ建物だったので、空襲の目標になると心配され、校舎の壁を地味な色に塗りかえたり、近くの工場を教室として貸してもらったりもしました。この頃言問小に通う子供たちの数はわずか60人ほどだったそうです。
昭和20年3月9日から10日にかけて、東京大空襲がありました。本所区は軍隊の物資を作る工場が集まっていたので、特に集中的に爆弾を落とされました。本所区のほとんどが焼け野原になり、小学校も小梅小と言問小以外は全て焼けてしまいました。卒業を間近にして、地域に戻っていた6年生も空襲に巻き込まれたそうです。
千葉にいた子供たちは、さらに安全な場所を求めて岩手県江刺郡(今は市)の黒石村にあった正法寺に再疎開しました。

3 戦争が終わって
昭和20年8月、長かった戦争が終わりました。次の年の3月には子供たちも疎開先からもどってきました。しかし、食べ物も家を建て直す材料も不足し、苦しい生活が続きました。学校で勉強しようとしても教科書や鉛筆もありませんでした。
それでも、言問小学校は校舎が焼け残ったため、授業が続けられました。(牛島小学校は校舎が焼けてしまったため、このとき廃校となりました。)
昭和22年には新しい学校制度が始まり、中学校に全員が行くことになり、男女が同じ教室で勉強するようになりました。なお、それまでは男女別のクラスが普通でした。子供の栄養不足を解消するために学校給食も始まり、本所区と向島区とが一緒になって墨田区になったのもこの年のことです。
このころの言問小は、校舎が焼けてしまった他の学校に教室を貸していました。しかし疎開していた子供が戻ってきたため、子供の数は一気に多くなりました。教室が不足し、1,2年生は午前中に来るクラスと、午後から来るクラスとに別れ、一つの教室を2クラスで使う二部授業を行うということもありました。
4 町の発展と施設の充実
世の中が落ちついてきて、都電(道路を走る電車)が復活するなど、町の様子も戦争の前と変わらなくなってきました。
町には工場が建ち並び、たくさんの人が働いていました。しかし、工場から出るけむりや排水のため、空気や川のよごれ(公害)も目立ってきました。

言問小の校舎も少しずつ良くなり、給食室や放送室もこの頃に整備されました。
昭和38年(1963)、墨田区で一つしかない「きこえの教室」が作られました。窓を二重にした静かな環境で、今も通級指導が行われています。このころの言問小には約700人ぐらいの子どもが通っていました。
5 きれいな町と学校をめざして
公害が大きな問題になると、工場でも公害を出さない工夫をするようになりました。他の場所へ移る工場もあり、墨田区の人口は少しずつ減っていきました。
植物を大切にする町作りの一つとして、墨田区内の学校のコンクリートのへいが、ツツジなどの生け垣に変えられました。
また、小梅小など、戦争の前にたてられた校舎は次々と建てかえられました。しかし、言問小学校の校舎は大地震でも平気なぐらい丈夫だということで、そのまま残されました。言問の校舎は墨田区内でも一番古いものです。
開校45周年を過ぎたころから、教室の床のいたみがひどくなってきました。校庭もコンクリートのままでした。そこで。昭和58年の夏休みに、教室の床は今のようにはりかえられました。校庭もソフトアスファルトで舗装されました。
暖房機も変わりました。昭和48年(1973)までは石炭を燃やすストーブだったのが、ガスストーブになり、昭和62年には、同じガスを燃やすものでも、より安全な、F・F暖房機になりました。
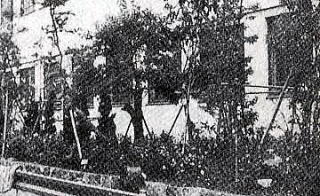
6 新しい時代をむかえて
平成に入って、言問小では学校の施設の改善が進みました。開けにくくなった窓はアルミサッシになり、校舎の外側は開校当時のように真っ白にぬり直されました。現在、教室には電子黒板が導入され、一人一台端末を活用した授業が行われています。

令和5年(2023)には、本校の校舎と講堂が国の有形文化財として登録されました。
これまでの85年の本校のあゆみを支えてくださった地域の方々がいつまでも誇りに思えるような学校であり続けたいと思います。
